真緒の場合
- [1] 真緒 腹部と乳房が丸見えになりました
- 先日、雨の中Tシャツ一枚でジョギングをしてきました。
白いTシャツだったので、完全無欠に透けて腹部と乳房が丸見えになりました。
当然周りからは、軽蔑、顰蹙の視線を浴びました。
- [2] ベンジー
- Tシャツのジョギングを実行したのだね。
思いっきり透けて腹部と乳房が丸見えになったか。
その姿を人に見られたのだね。
軽蔑や顰蹙にも、感じてしまったのかな。
- [3] 真緒 女湯に男性スタッフが入って来て
- 今春、大学を卒業し在京の某テレビ局に、アナウンサーとして採用された。
だが、今はまだ研修中の見習い女子アナウンサーだ。
今日は、先輩アナウンサーで指導員でもある、遠野香澄さんと供に、番組の取材で山奥の村へロケに来ていました。
移動だけでも数時間を要するため、私と遠野先輩、あと五人の撮影スタッフは、今夜村にある温泉宿に、一泊する予定になっていた。
「でもね、鷹野さん。今のままじゃ少し大人しすぎると思うの。もうちょっと、自分から前に出て行く姿勢があってもいいわね」
「はいすみません」
私は、幼い頃から、引っ込み思案なところがあり、自分でも気にはしているが、ついつい人の後ろに回りがちだった。
指導係の遠野先輩には、いつも同じことを注意されている。
「はい、お説教は以上。今日の旅館は露天風呂ですって。楽しみね」
遠野先輩が表情を変え、楽しそうに微笑んだ。
遠野香澄(先輩)は、二十九歳の中堅アナウンサーで、なかなかの美人で人気もある人だが、偉ぶったところもなく穏やかで優しい先輩だった。
「はい、御一緒させて頂きます」
優しく微笑む先輩に、私も笑顔返す。
元々、今日のロケのキャスティングは、遠野香澄と新人タレントが、担当するはずだったのだが、香澄(先輩)の推薦で私が出ることになったのです。
私は厳しいながらも、優しい心配りを忘れない香澄(先輩)に憧れていたのです。
「おーい、みんな早くバスに乗れよ、置いていくぞ」
運転手の小峰さんが、皆を急かすようにロケバスから首を出している。
「さあ行くわよ、鷹野さん」
香澄に手を取られ、私はロケバスに向かって駆け出していった。
「ああ、いい気持ち」露天風呂にタオルで前を隠した身体を沈めて、私は大きく背伸びをした。
大小の岩に囲まれた露天風呂は広くはないが、苔むした岩や木々に囲まれ、なかなかいい雰囲気だった。
「あら、おじゃまするわね」
脱衣所の戸を開けて入ってきたのは香澄だった。
自分と同じように、裸体をタオルで隠している。
「あ、お先にお風呂頂いてます」
私は、慌ててぺこりと頭を下げた。
「そのままそのまま、仕事は終わったんだから気を遣わないで」
「すいません」
乳房の大きさもほどよく、ウエストもよく締まっていて、バランスのとれた見事な肢体だ。
「おばさんですけど。失礼しまーす」
香澄(先輩)は、ふざけた調子で笑いながら湯船に入り、私の隣に座った。
「いい気持ちね」
「ええ、ほんとに」
二人は、夕焼け空を見上げて、気持ち良さげに息を吐いた。
「ねえ、鷹野さん、あなた何でアナウンサーに、なろうと思ったの?」
「えっ、理由ですか・・・・・・?」
「そうよ、最近、局アナになろうって女の子は、上昇志向が強い子か、あとは玉の輿に乗ろうって子ばかりだもの。でも、あなたはどちらでもない気がするのよ」
私は答えに詰まった。
香澄(先輩)の予感は見事に当たっている。
自分は子どもの頃から大人しく、人前に立つような性格ではなかった。
「鷹野さん、鷹野さん大丈夫、どうしたの?」思い詰めた表情で、下を向く自分に香澄が慌てて声をかけてきた。
「すっ、すいません。ちょっとのぼせちゃったみたいで・・・・・・」
香澄の声で我に返った私は、慌ててごまかした。
「私、答えづらいこと聞いたかしら・・・・・・」
「いえ、全然、そんなことありません」
心配そうに見つめる香澄に、私は申し訳ない気持ちでいっぱいだった。
「うーん。しいて言えば玉の輿かな」
「まあ、ちゃっかりしてるのね。あははっ」
「あははっ、すいません。ちゃんとしてなくて」
他に誰もいない気安さもあってか、二人は少女のように屈託なく笑った。
「鷹野さんは彼氏いるの」
香澄が、笑顔で聞いてきた。
局内では師弟関係も同然なので、仕事を離れて女同士として、触れ合っているのが楽しいのだろう。
「いえいえいません」
私は、慌てて手を顔の前で振った。
「ほんと。こんなに可愛いのに」
「本当に。まったくなんですよ」
可愛いと言われ、私は顔を真っ赤にして否定して言った。
お嬢様育ちの私は、異性と付き合ったことがない。
女子校育ちならなおさらだった。
勿論いまだ男性と一夜を共にした経験もなかった。
「肌だってこんなに綺麗なのに、もったいない。私なんかもうおばさんで、嫌になっちゃうわ」
香澄の手が私の、首筋あたりに触れる。
「あん、先輩くすぐったいですよ」
私は、くすぐったさに身体をくねらせながら、香澄の手を払った。
「うふふ、案外敏感なのね」
香澄(先輩)は、急に立ち上がると、私のタオルを掴み、一気に身体から剥ぎ取った。
「きゃっ、何するんですか先輩、やめて下さい!」
全裸にされた私は、飛び上がって香澄(先輩)の手からタオルを取り返そうとするが、香澄(先輩)は一瞬早く手を背中に回してタオルを隠してしまった。
「ふふ、思ったとおり大きいオッパイね。Eカップはあるかしら」
飛び上がった反動で、大きな乳房がぷるんと揺れた。
重力に逆らうように上に向かって隆起し、先端にあるピンクの乳頭は露天の空を向いていた。
「オッパイは、大きいのに下は薄いのね。なんだか、子供みたい」
「ああっ、いやっ」
私は、慌てて股間を手で覆った。
私の秘毛は、二十三になった今も、生え始めの中学生のように薄く、女の裂け目が薄っすらと覗いて見えるほどだ。
私も、自分の秘毛の薄さにはコンプレックスを持っていて、だからこうして人と一緒に風呂に入ることが、あまり好きではなかった。
「先輩・・・・・・」
いい加減にして下さいと、香澄(先輩)に言いかけて思わず息を飲んだ。
最初はふざけているのかと思った香澄(先輩)の様子が、あきらかにおかしいのだ。
いつもの優しい、微笑みをたたえた顔とはうって変わって、口元はゆがみ、目は妖しげに光っている。
「うふふ、今頃、隠したって無駄よ。もう、バッチリみんなに見られたわよ」
「み、みんなって・・・・・・」
「うふふ、もういいわよ。出てきても」
香澄(先輩)が大声をあげると、露天風呂を囲む木々の間から、草をかき分ける音が聞こえ、岩の裏から次々に人影が現れた。
「きゃああああ・・・・・・」
私は、大きな悲鳴をあげ、そのまま膝を曲げてしゃがみ込んでしまった。
「ヒヒヒヒヒヒ・・・・・」
薄気味悪い笑い声と共に、露天風呂を取り囲むように現れた男達は、全員が今日のロケスタッフで、中にはカメラを手にしている男もいた。
「いったい、何のつもりです。どうしてこんな・・・・・・」
あまりの恥ずかしさに、身体を丸めたまま、私は岩の上に仁王立ちする、ディレクターの小峰を見た。
小峰は、この現場の責任者だ。
「ふふ、番組のチームワークのために、身体でスキンシップをとろうと思ってね」
「そ、そんな・・・・・・こんな非常識なことが、許されると思っているのですかっ!」
「ふふ、心配ご無用。旅館の人間とも話はついているからね。ここの人達は何を見ても何も言わんよ。だから、今夜は心ゆくまで楽しもうじゃないか。鷹野アナ」
ジーンズ姿の小峰が言うと、全員がニタニタと笑い始めた。
「あ・・・・・あ・・・・・・あ・・・・・・」
見渡せば、今日のスタッフは全員ここにいる。
ということは自分に味方をするものは、旅館の者を含めて一人もいないということだ。
恐ろしさのあまり足が震えだした。
「いやっ!」
追いつめられた私は叫ぶなり、脱衣所に向かって駆け出した。
- [4] ベンジー
- ロケで泊まった旅館の露天風呂で、先輩アナにタオルを取り上げられたのだね。
それどころか、男性スタッフにも囲まれてしまったか。
男性経験のない真緒にとっては、かなり辛い状況だったようだ。
旅館の人も味方してくれないようだし、むしろ先輩や男性スタっフと一緒になって、真緒に恥ずかしい思いをさせて来そうだね。
脱衣室に向かって逃げ出したのは良いが、さて、真緒を脱いだ服はどうなっているのだろうね。
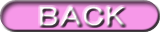 |