真緒の場合
- [1] 真緒 全裸で座卓に縛られて
- 「あっ、待て!」
近くにいたADが、洗い場に飛び降りて私を、取り押さえようとしたが、私は、その手を振り切って、脱衣所に飛び込んだ。
私は、着てきた浴衣には目もくれず、そのままの格好で廊下に飛び出した。
割り当てられた部屋は、廊下を曲がって突き当たりの部屋だ。
今、服の心配をするよりも、部屋に戻り荷物を取って、逃げ出す方が先決だと考えた。
「はあ、はあ、はあ」木造の古い建物の縁側を兼ねた廊下を、私は必死に駆け抜ける。
自身の足が木の床を蹴り上げるたびに、乳房が大きく揺れる。
(もうすぐ――)
後ろからはまだ、足音は聞こえてこない。
廊下を曲がればすぐに私の部屋だ。
私は救われる思いで、角を曲がった。
「あっ!」
廊下を曲がったところで、私は息を飲んで立ち止まった。
部屋の前には立ちはだかるように一人の男が立っていたからだ。
でっぷりと太った身体を、浴衣に包んだ中途半端な長さの白髪頭の男は、現某テレビ局長、北山光夫だった。
「おや、新人アナの鷹野君じゃないか。そんな格好でどうしたね」
北山はニヤリと笑うと、湯に濡れたままの私の裸を、上から下、下から上に舐め回してきた。
「あ・・・・あっ・・・・・・これは・・・・・・」
私は、慌てて身体を隠してうずくまる。
「おやおやこんな公共の場所で全裸とは、君は露出狂かね」
言葉とは裏腹に、北山は私の裸体から片時も、目を離そうとはしない。
「いっ、いやっ、見ないで下さい」
徐々ににじり寄ってくる北山に、確かな恐怖を感じた私は、再び立ちあがって最初に来た方向を向いた。
「ひっ」
だが、そこには香澄と男性スタッフが、ニヤニヤ笑って立っていた。
前後をふさがれた私は、もうどうすることも出来なかった。
その場で力が抜けたように床にへなへなと、座り込んでしまった。
男達は、へたり込んだ私の四肢に、手をかけると数人で、神輿のように担ぎ上げた。
「わっしょい、わっしょい」
男達はかけ声をかけながら、私の身体を揺らして、廊下を練り歩き、北山や香澄はその後に続いた。
「よ――し。縛り上げろ」
宴会場代わりの大広間に担ぎ込まれた私は、部屋の中央に置かれた大きな座卓に乗せられた。
「あ、ああ、いやあああ・・・・・・やめて・・・・・・」
すでに準備をしておいたのだろう。
座卓の脚には、それぞれに短いロ―プが結んであり、男達は私の手首や足首にそのロ―プを巻きつけ始めた。
「やめてっ、こんな。いやあああ・・・・・・」
男達は暴れる私をものともせずに、馴れた手つきで私の手足をロ―プに固定していく。
私は、必死に抵抗を試みるが、男数人の力には逆らい切れるはずもなく、あっという間に縛り上げられてしまった。
「ふふ、すごい格好ね。鷹野さん」
香澄は両手足を大の字に固定された私を、嬉しそうに見下ろしていた。
そして、ロ―プによって両手足を開かれた部分をじっと見つめている。
そう、恥ずかしいまだ未開の部分まで、全てを晒されているのだ。
「ああっ、お願い見ないでぇ・・・・・」
絶叫して首を振るが、四肢を固定したロ―プがぎしぎしと鳴るだけだった。
「綺麗なオマンコね。毛も薄いし、処女みたいね。ね、局長、最初は私に任せてくれませんか?」
「いいぞ、好きにしろ」
香澄の提案に、北山は笑って頷いた。
- [2] ベンジー
- 全裸のまま、浴室から逃げ出したのだね。
服を着ている余裕はなかったか。
でも、部屋の戻る前に捕まってしまったわけだ。
男性スタッフに、神輿のように担ぎ上げられた時は、生きた心地がしなかったのではないかな。
でも、それも序の口か。
大広間の座卓に、大の字磔にされてしまったのだね。
女の子のすべてを晒して、「最初は私に任せて」なんて、何をされるか、恐怖でしかないね。
- [3] 真緒 処女を散らされました
- 「ありがとうございます。じゃ鷹野さん、本番の前に私が優しくほぐしてあげるからね」
淫靡に笑う香澄が、バスタオルを脱ぎ捨て全裸になると、私の股間に顔を寄せてきた。
「うふふ、とっても綺麗、女の私もほれぼれするわ」
香澄は、うっとりとした口調で言うと、指先を私の秘裂に差し込もうとする。
「あ、ああっ、いやあああ・・・・・・」
処女地を荒らされる、恐怖に私は腰を上下に振って、指を振り払おうとした。
「大丈夫よ怖がらなくとも。優しくしてあげるから」
香澄が優しい言葉をかけながら、うっとりとした表情で、私の唇に自分の唇を重ね合わせてきた。
そして、そのまま身体を下にずらすと、仰向けに寝ていても大きく盛り上がっている、乳房に舌を這わせていく。
「あっ、だめっ・・・・・・あっ」
香澄は、あくまでソフトな手つきで乳房を揉み、ピンクの乳頭を吸い上げる。
同性のツボを心得た愛撫に、私は艶のある声をあげてしまった。
「ああ・・・・・いっ・・・・・・ああっ」
意思に反して喉の奥から、沸き上がる喘ぎ声を、必死に首を振って拒絶しようとしたが、香澄の舌が触れるたびに、どうしょうもなく声が漏れてしまうのだ。
「うふふ、結構敏感なのね。じゃあここはどう・・・・・・」
香澄は自分の乳頭を、私の乳頭に擦りつけるようにして、身体を重ね合わせながら、右手の人差し指をそっと閉じた秘裂へと這わせてきた。
「あ、やっ、あっ」
身体がビクッとうねる。
香澄の指が触れると同時に、経験したことのない痺れに背中が震えた。
「あら、濡れてる。けっこうスケベなのね」
私の敏感な反応を面白がるように香澄が今度は、指で肉唇を押し広げて肉芽を剥き出しにし、ゆっくりと擦りあげる。
「あっ、ああっ、ひあああ」
背中を激しい痺れが駆け抜けた。
私は、生まれて初めて味わう強烈な刺激に、逆らうことも出来ずに喘ぎ声をあげてしまった。
「あらあら、エッチなお汁がどんどん出てくる」
「ああっ、いや、やめてえええ」
「鷹野さん、アナウンサーは嘘ついちゃダメよ。ほんとは気持ちいいんでしょ」
香澄は肉芽を押さえたまま、空いた指で私のピンクの裂け目をすっとなぞった。
「ああ、ああっ、あんんん」
「こんなに感じてるくせに、やめてなんて言っちゃダメ」
「そ、そんな、ああっ、ああああ」
私は必死で、香澄の言葉を否定しようとするが、指が媚肉を這い回るたびに、全身が熱く燃え上っていく。
「んん、くあ、ああん、あっ、あっ」
快感に対する免疫がないので、子宮を震わせる刺激に抵抗する術がないのだ。
「うふふ、みんなが見てるわよ」
「あっ、ああっ、いやあああ、見ないでえええ・・・・・・」
香澄に言われうっすら目を開けると、局長の北山をはじめ、スタッフ全員が座卓の周りに立って、大股を広げる自分を見ていた。
「ああっ、んあ、ひん、ああ」
私は、羞恥と屈辱感が入り交じったような気持ちになり、涙を流して叫んだ。
しかし、身体の高ぶりは収まるどころか、加速していく一方だった。
「そろそろ、いいかな」
秘裂を嬲る手を止め、香澄は顔を上げた。
「うふふ、すごい濡れようね鷹野さん」
「そ、そんな濡れてなんか・・」
「本当よ。ほらこれが、何よりの証拠」
私の、反論に答えるように、香澄はにっこり笑うと、私の眼前に自分の指を突き出してきた。
香澄の指先には透明な粘液が、大量に絡みつき、湯気を立てている。
「いやっ!」
目の前の現実に私は、慌てて目を逸らしてしまった。
香澄の手についている粘液が、自分の身体から溢れ出たものだと、いうことはハッキリと判っていた。
「お豆はとっても敏感みたいね。じゃあここはどうかしら」
羞恥に震える私の姿を、しばらくの間楽しんだ後、香澄は指を二本合わせて、私の未踏の媚肉へと差し入れてきた。
「んぐっ、んあ」
指が侵入するのと同時に、秘孔の中程で何かが弾けるような感触があり、身体を裂かれるような、激痛に背中を仰け反らせた。
「あら、うそ・・・・・・」
慌てて指を引き抜いた香澄が、自分の指先に付着しているものを見て驚きの声をあげた。
「まさか・・・・・・鷹野さん、本当に処女だったの?」
「うっ・・・・うっ、ううっ・・・・・・うあ・・・・・・」
香澄が、差し込んでいた二本の指には、処女の証である赤い鮮血がついていた。
指先の赤い血を見た私は、涙が?を伝って落ちるのが判った。
「ごめんね、鷹野さん許してね」
本当に申し訳なさそうに香澄が言った。
流れ落ちる私の涙を指先でそっと拭う。
驚いているのは香澄だけではない。
一部始終を見ていたスタッフも、涙を流している私に同情するかのように、言葉をなくしていた。
- [4] ベンジー
- 座卓に大の字磔にされたら、無防備のハダカを見られるだけでは済まなかったね。
香澄先輩の手で愛撫されて、感じさせられて、アソコもいっぱい濡れさせて、
とうとう破瓜してしまったか。
これは辛かっただろうねる
まさか、香澄先輩も、真緒が処女だとは思ってもみなかったようだ。
周りで見ていたスタッフも、真緒に同情してくれたようだ。
さて、大の字磔からは解放して貰えたのかな。
- [5] 真緒 身体中を甘痒い痺れが駆け巡る
- 「ふふ、遠野君、まあそんなに案ずることはない」
「局長・・・・・・」
「どちらにしても鷹野君は今日ここで、ワシに貫かれるんだ。指が早いかチンポが早いかの違いだけだ」
北山だけは、同情する様子も見せずに笑顔で言った。
「君が鷹野君に申し訳ないと思うなら、ワシと交わる前に鷹野君のオマンコを、少しでもほぐしてやるのが、優しさだと思うのだがね」
北山は、励ますような口調で言いながら、裸の香澄の肩を軽く叩いた。
「そうですね。鷹野さんのバージンはもう帰ってきませんものね。判りました。こうなってしまったからには、精一杯がんばって鷹野さんを、燃え上がらせて見せますよ」
「ふふ、頼むぞ」
「はい。任せて下さい」
香澄は開き直ったように、北山に強い返事を返した。
そして、両手の指を使って鮮血が絡む私の、肉唇を押し広げていった。
「いや、いやいや、もうやめてえ・・・・・・お願いよ・・」
傷ついたばかりの媚肉を広げられ、私は引きつった悲鳴をあげた。
また、さっきの激痛を味わうかと思うと、もう生きた心地がしなかった。
「ああ、先輩。わたしに、私に同情してくれるのなら、もうやめて・・・・・・」
香澄に涙声で訴えた。
「だめよ鷹野さん。このままじゃあなた、エッチが嫌いになってしまうわ。そうならないためにも、今から、私がセックスの素晴らしさを教えてあげるから」
「そんな、私、もう、ああっ」
もう嫌いになっています。
私が言おうとしたその言葉は、喉の奥から沸き上がる嬌声に遮られてしまった。
指で広げた媚肉に向かって、顔を沈めた香澄の唇が、私の肉芽を包み込んだのだ。
「ああっ、やめ、ああっ、ひあ、ああん」
先ほどの激痛とはうって変わり、身体中を甘痒い痺れが駆け巡る。
つらい痛みの後だけに、痺れはなんとも心地よく、私の身体はあっという間に燃え上がっていった。
「どう気持ちいいでしょ。鷹野さん」
さらに香澄は舌先も使って私の、肉芽を責め立ててくる。
舌のざらついた部分が触れるたびに腰骨に電流が走り、下半身がバラバラになってしまうかと思った。
「む、んああ、ひん、いいっ、ああっ、ああ」
肉芽を舐められているだけなのに、腰回りが全体が熱くなり、子宮も燃えて溶けそうだ。
未知の快感に苛まれる私は、完全に自分を見失っていた。
「嬉しいわ鷹野さん、とっても感じてくれてる。血とは違うスケベな液が出ているわ。ほらお尻の穴まで垂れてきた」
私の秘裂から放たれる淫臭に、周りを取り囲む男達も興奮しているようだ。
「もっと、もっと感じてちょうだい」
香澄が再び蕾を口に含み、さらに指で秘孔を刺激し始めた。
「ひあ、こわっ、怖い、あっ、ああっ、ああん」
香澄の指は傷ついた処女膜を避け、入口あたりの媚肉を巧みに刺激している。
- [6] ベンジー
- みんなが同情する中、北山だけは、やる気満々と言うわけだ。
そのために、オマンコをほぐすように言われた香澄先輩も大変だね。
でも、もっと大変なのが真緒だ。
手足を拘束されたまま、さらに恥ずかしいことをされてしまうのだね。
今度は痛みを伴わないように、優しく扱われて、セックスの良さを感じられるようにほぐされるか。
どっちにしても、恥ずかしいことには変わりないようだ。
気持ち良くなっていったようだね。
でも、それが感じるということなのかもわからず、怖さだけが先行していたようだ。
後は、香澄先輩の手技次第と言ったところかな。
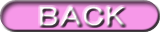 |