容子の場合
- [1] 容子 エクスタシーを迎えました
- 堀田の抽送に合わせて、その豊かな乳房は大きく揺れ、くの字に曲げられた真っ白な両脚の足先は、ベッドの上につま先立ちになっている。
私は、ついにその思考を完全に奪われ、もう後は頂点を向かえるだけとなっていた。
「ああ、だめ、ああああ」
ついに、その両太腿が激しく痙攣を始め、それを感じた堀田は腰を大きく前に突き出すようにして、さらに私の最奥を突き立てていく。
「ああ、ああっ、だめえ、あああイッちゃう、イッちゃう、ああ、イクううううう」
堀田の命令通り、私はスタジオの奥まで響き渡るような大声で叫ぶと、全身を激しく痙攣させ女の絶頂を極めた。
その声を聞いた堀田はニヤリと笑い、私の秘裂からその逸物を引き抜くと、凄まじい勢いで、私の大きく盛り上がる乳房にその精をぶちまけていく。
「ああ、ああああ」
堀田の生暖かい淫液が乳房に降り注ぐのを感じながら、私はがっくりと顔を横に伏せ、エクスタシーの甘い余韻に唇を震わせた。
「曽賀アナ、いまエクスタシーを迎えましたね」
私の、絶叫を聞いた室田が慌てて駆け寄ってきた。
私は、先ほどの一度目の時と同じように、ショックで口を開くことが出来ず、ただ哀しげに肯いただけだった。
「勝者、堀田五郎」
「よっしゃあぁぁー!!」
室田が、ボクシングのレフェリーをまねて、堀田の腕を上に向かって掲げると、堀田は、あいている方の腕を上に向かって、突き立てて勝利の雄叫びを上げた。
「はい、カットです」
大井の大声がスタジオ中に響き、私のあまりのエクスタシーに、金縛りにあったように、動けなくなっていたスタッフが、ほっと息を吐いて動き始めた。
いまだ手枷と鎖によって両腕を引き伸ばされたまま、つらそうに顔を横に伏せている自分のところに、おしぼりを持ったスタッフが駆け寄り、私の双乳の上に散乱している白い粘液を拭き取り始めた。
「ふん、イクーだなんて、よくあんな大声で叫べたものね。
これでわかったでしょ。
キャスターだなんて気取っていても、所詮、あんただって私達と同じなのよ。
あっ、でも私達の中にも人前で、あんな大声出す子いないもんね。
実はあんた、相当の淫乱じゃないの。
あはっはっはっ」
涼子は、口汚く私を罵ったあと、大声で笑い出した。
「ああ、そんな・・・・・・」
スタッフに、身体を拭かれている間もずっと、哀しげに身体を震わせていた私は、涼子の言葉に追い打ちをかけられ、今にも泣きだしそうな切ない声を上げた。
年下の、人間から淫乱と罵られても、何も言い返せないような、淫らな姿を晒してしまった自分自身が、哀しかったのだ。
- [2] ベンジー
- とうとうイってしまったね。
と言うか、最後は割と簡単に上れ詰めてしまったようだ。
思っていたよりずっとエッチだったのかな。
大きな声で「イクー」と宣言してしまったし、それを大勢に聞かれてしまったし、もう容子はキャスターだなんて名乗れないかも。
涼子の言う通り、相当の淫乱だったのだね。
さて、その哀しみの後に、罰ゲームが待っているのだよね。
- [3] 容子 アヌスを嬲り抜くつもりなの
- 厚く空を覆う雲から大粒の雨が、絶え間なく高層マンションビルの、分厚いガラス窓を叩いては、ベランダのコンクリートを流れていく。
お昼過ぎに浅い眠りから覚めた私は、そんな風景をリビングのテーブルに座り、ただぼんやりと眺めていた。
あの地獄の絶頂の日から、もう一週間が過ぎようとしていた。
女肉はおろか、その腸内までも公開したあの日の収録は、あまりの内容の濃さのため、収録後、すぐに二周に分けて放送することが決まり、私は室田から丸々二周間の休暇を与えられていた。
ここのところ毎日、眠りから覚めた私は、どこ出掛けることもなく、ただぼんやりと窓の外を眺めている。
こうしていると、失神姿までもカメラの前に晒してしまったあの日の収録の日が、まるで夢の中の出来事のように思えてくるのだ。
だが、しばらくすると、自分の惨めな姿をあざ笑う堀田や鮫島の顔が脳裏に蘇ってくる。
そして、あの日からもう、何度目かの涙が自分の頬を流れ落ちた。
私は、あの出来事が夢であって欲しいと何度も思うのだが、あの日、快楽に身を任せ、最後には自分から、淫靡な責めをねだったという事実が、何度、目覚めてみても現実であることに変わりはなかった。
(ああ、恥ずかしい)
私は、情けない気持ちで一杯になりながらも、取り敢えず身体を清めようと、重い身体を引きずるようにしてバスルームに向かった。
パジャマと淫液に汚れたパンティーを、洗濯かごに放り込むと浴室に入り、壁についているシャワーを全開にして熱いお湯を頭から浴びた。
私の、黒髪はあっという間にずぶ濡れになり、首やうなじにべったりと絡みついていく。
私は、それでも構わずにバスルームのタイルの壁に、両手をついたまま熱いお湯を浴び続けた。
(ああ、これじゃあ、あいつらの思う通りじゃないの)
絶頂を極めた私は、室田が自分に鮫島の家での集まりに来ることを、強制しなかった意図に気づいていた。
おそらく、室田は被虐の悦びに目覚めた私が、自分の欲望を押さえきれずに自ら、鮫島の所に来ることを確信していたのだ。
「ああ、情けない・・・・・・」
私は、シャワーを浴びながらそう呟いた。
私の、脳裏には勝ち誇る室田や鮫島の、笑い声が何度もこだましてくる。
「このままじゃ、私の負けじゃないの・・・・・・」
自分に言い聞かせて、心を落ち着かせようとするが、続いてあの鮫島の言葉が浮かぶ。
『ふふ、いい尻の穴だ。ワシはここが大好きなんじゃ、くっくっくっ』
(ああ、鮫島の家に行ったらきっとここを・・・・・・)
私が、集まりに参加すれば、きっと鮫島は私のアヌスを嬲り抜くつもりに違いない。
そう考えると、身体が恐怖に震えてくるのだが、私はアヌスの快感への興味を押さえきれずに、指できつくすぼまる裏門に触れてしまった。
「あっああっ」
指がその場所に触れる。
同時に切羽詰まったような叫び声を上げた。
「そんな・・・・こんなところで感じるなんて」
私は、ただの排泄器官のはずの裏門から、沸き上がる淫らな感覚を必死になって否定した。
だが、この前の収録の時に、堀田の操るカメラ付きのプラスティック棒で、目覚めさせられた肛門責めの快感を、私の身体はしっかりと覚えていたのだ。
「あああ、あああ、ああっ」
- [4] ベンジー
- 地獄の絶頂か。
容子にとっては、ホントに地獄だったのだね。
ちょっと酷い目に遭ったとか言う程度のモノではなかったか。
二週間の休みも、かえって残酷だったのではないかな。
忙しい方が良かったかも。
次の責めはアヌスか。
それを知っていても参加してしまうのだろうね。
肛門責めの快感を味わいたくて。
- [5] 容子 その格好で家から来たのか、って
- 再び自分の、意志を裏切るように動き始めた右手の指が、セピア色のすぼまりを押し込むたびに、秘裂とはまた違う甘い痺れが背骨を駆け抜け、両膝がガクガクと震え始める。
ついには、立っていることも難しくなり、私は壁に手を付いたまま、その場にへたり込んでしまった。
壁に手を付いたままタイルの床に膝を付き、四つん這いのような姿勢になったことで、私の二つの乳房はまるで釣り鐘のように、身体が動くたびに前後左右にフルフルと揺れ動く。
そして、それを二つに引き裂く割れ目の、中央にあるセピア色のすぼまりに真っ白な指が出入りするたびに、肉と肉の擦れ合う淫らな音が、浴室に響き渡った。
「あああ、だめえ、あぁぁぁ・・」
私は、裏門の快楽を否定しようと声を上げるが、右手の指はどんどん腸の中へと向かっていく。
「ああっひいっ、ひっ、あぁぁぁ・・・」
アヌスを擦り上げる、何ともいえない感覚に酔いしれ、私はまた自制心を失っていた。
(ああ、もうダメ。我慢できないぃぃぃ)
差し込んだ、指を激しく出入りさせながら、自分自身の腸をまさぐり続ける。
指の腹が敏感な腸の粘膜に触れるたびに、腰骨ごと溶けてしまうかと思うほどの電撃が沸き起こり、そのあまりに激しい快感は、自分の心の中にあるキャスターとしてのプライドも、そして、自分を罠にはめた鮫島や室田を恨めしく思う気持ちをも、あっという間に溶かしていった。
「あ、あ、あぁぁぁ」
今まで、自分を支え続けてきた意地やプライドを、肛虐の激しく妖しい快楽に完全に破壊された私は、もう完全に快楽を貪ることしか、考えられなくなり、大きく収縮を繰り返すアヌスに深々と突き刺さった指を、さらに奥へと向かって突き立てていく。
「ああ、いいっ、あぁぁぁ・・・・・・いいっ」
そして、ついに私は、腰に全く力が入らなくなり、再び意識が遠のき始めた。
「ああっ、いっ、いっ、いっ、イクううううう」
背中を大きく仰け反らせ、乳房や太腿を痙攣させながら、激しく女の絶頂を極めた私は、シャワーから流れ落ちるお湯で、水たまりと化しているバスルームの床にその身を投げ出した。
「ああ、はあ、はあ、はあ」
立て続けに二回もの絶頂を極めた私は、さすがに疲れ果て肩で息をしながら、やっとの思いでふらふら立ち上がると、シャワーの蛇口に手を伸ばした。
そして、どしゃぶりの雨のように流れ続けるお湯を冷水に換えると、肌を刺すように冷たい真水を全身に浴び始めた。
「うっ、うっ、あぁぁぁぁぁ」
冷水によって身体の熱が冷めていくのを感じながら、私は溢れる涙をもう抑えようともせずに号泣し始めた。
「ああぁぁ、うあぁぁぁ」
冷水を浴びながら、私は数分もの間、泣き続けた。
ひとしきり泣いた後、やっとその場で立ち上がると、シャワーの蛇口を閉めた。
シャワーを止めた私は涙を拭き、水に濡れてすっかり重たくなった、髪の毛を後ろで束ねると胸を張って顔を上げた。
しっかりと前を見つめる自身の目は、胸のうちに秘めた決意を示すかのように鋭く光輝いていた。
自ら、室田に電話をして集まりに参加する旨を伝えた。
室田のマンションに到着すると、インターフォンを鳴らした。
ドアが開き室田が現れ、
「お待たせしました…あ、ああ・・・・・・」
マンションの扉の前で、丁寧な言葉遣いで頭を下げる、私の姿を見た室田は、驚きのあまり言葉を詰まらせてしまいながら、呆然と立ち尽くしていた。
いつものように、きちんとセットされた黒髪や、切れ長の瞳、そして、少し潤みを帯びた唇。
そこまでは、いつもとまったく同じであったが、室田を驚かせたのは、私が身につけている、服装だった。
私の、大きく前に突き出した巨大な乳房を覆っているのは、薄手の白い生地で出来たタンクトップ一枚なのだ。
しかも、乳房の周りの布地はすべて切れ込んでおり、私の重量感のある乳房の横の部分や、二つの肉塊がぶつかる谷間は完全に露出している。
さらに生地が薄いので、乳房の頂点にある乳頭の形が、白い布地にくっきりと浮かび上がり、私がブラジャーを着けていないことは、誰の目にも明らかだった。
そこからウエストにかけてくびれを描いて、大きく盛り上がる腰回りには、ジーンズ生地のミニスカートが、ぴったりと張り付いている。
スカートは極端に丈が短く股下はないに等しかった。
これでは、ストッキングを履いていない両脚が、剥き出しになるだけでなく、少しかがんだだけで、股間が周りの人目に晒されることになるのは、火を見るより明らかだった。
「君は、その格好で家から来たのか」
室田は、かすれる声を絞り出して言った。
「はい、電車で来ました」
そう答えた私の言葉に、室田は再び、口をぽかんと開けたまま絶句した。
「ま、とにかく上がりたまえ」
震える声でそう言うと、玄関に立ったままの私を、部屋に招き入れた。
「失礼します」
履いてきたヒールを脱いで室田の後について部屋に入った私と、室田は向かい合って立った。
- [6] ベンジー
- すっかりオナニーを楽しんでしまったのだね。
しかも止められなくなったか。
自制心も失ってしまったのだね。
アヌスまで擦り上げて、快感を貪っていたのだね。
キャスターのプライドも何も、失くしてしまったようだ。
そして、自ら室田の集まりに参加する旨を電話してしまったか。
それもかなり恥ずかしい恰好だったのだね。
薄手の生地でできたタンクトップ一枚か。
とても電車に乗れるような恰好ではない。
さて、集まりではどんな辱めが待っているのかな。
- [7] 容子 濡れていたら奴隷なる条件で
- この、部屋は都心のワンルームしては広い上に、部屋には仕事用の机とベッドぐらいしか置いていないため、二人が向か合っても充分に余裕があった。
「もう、私の聞きたいことはわかっているだろう。どうして君はそんな格好で、しかも電車なんかで、ここに来たんだ」
私の、あまりに変わり果てた姿を目の当たりにし、自分が、とても冷静でいられないことを、感じている室田は、もう遠回しなことは言わずに、はっきり本音で聞いてきた。
室田の質問に、頬を赤らめ、恥ずかしそうに顔を伏せた。
そして、唇をゆっくりと開いた。
「室田さん、私はずっと、涼子さんのように大勢の人の前で平気で肌を晒して、しかもそれを日々の糧にしているような、人間を軽蔑してきました。でも、私自身が、人前で何度も絶頂を極めるうちに、もう自分自身がわからなくなってきたのです」
震える声で言い、さらに羞恥に全身を赤く染めながら言葉を続ける。
「キャスターとして、社会悪と戦い、信念を貫き通す自分が私は好きでした。そんな自分とは正反対の自分・・・・・・あんな、恥ずかしい仕打ちを受けながら、感じてしまう自分が確かにいるんです」
そこまで言うと私は顔を上げ、前に立つ室田を、すがるような眼差しで見た。顔を上げたことでタンクトップからは白い胸元が覗き、いまにもその巨乳が弾け出てきそうだった。
「だから私、自分自身にけじめをつけるために、こんな恥ずかしい格好で街を歩き、電車に乗ってここまで来たのです。もし・・・・・・自分がこんな格好を人目に晒して、その・・・・・・下着を濡らしてしまったら・・・・・・その時は、もう、私が、変態だということを認めようと思ったのです」
あまりの恥ずかしさに、途切れ途切れになりながら、私はそう言い終えると、再び下を向いて瞳を瞬かせた。
「それで、電車の中ではどうだったんだ」
室田の言葉に私は、再び口を開く。
「電車の中では、座れたので、ずっと寝たふりをしていたんですが・・・・・・目を閉じていても男の人の視線を、痛いほど感じて恥ずかしくて死にそうでした。そして、私のことを変態女だと言う女の人達の声が聞こえてきて・・・私もう哀しくて、涙が出てきました」
その屈辱が思い出され、瞳から涙が溢れ出た。
「確かにそれで感じたら立派なマゾヒストだ。それで、もう結果は見たのか」
室田は興奮気味にそう尋ねた。
「それは・・・・・・まだ・・・・・・怖くて確かめていません。下着も生地の厚いものを着けてきたので、自分でもよくわからないのです・・・・・・それに今日は初めから・・その・・・・・・室田さんに」
私は、そこまで言うと言葉に詰まり、黙り込んでしまった。
「それを俺に、確かめろというのか?」
室田が声をうわずらせながら言うと、私は顔を伏せたままこくりと頷いた。
「よし、心して検分させてもらおう」
そう言うと室田は、私の両脚の前にしゃがみ込む。
「ま、待ってください」
私は慌ててミニスカートの裾を押さえて、しゃがみ込もうとした室田を制した。
「待って下さい、室田さん。もし、下着が濡れていなかったら・・・・・・濡れていなかったらその時は、私のお願いを聞いてくれますか?」
股下のほとんどない、恥ずかしいスカートの裾を必死で押さえながら、私がそう言うと、室田は身体を起こして深く息を吐いた。
「ああ、わかっている。もし濡れていなかったら、あの契約書を破棄して、君を本局に戻してやろう。鮫島先生の説得も蒲池局長への交渉も俺が引き受ける」
OXテレビに戻れると聞いて、無意識に安堵の表情を浮かべた。
「だが、濡れていた時はわかっているな。君はマゾであることを認めて我々の牝奴隷になるんだ」
お前が、感じていた時は容赦はしない。
室田は、その決意を表すように眉間にしわを寄せて、強い口調で私にそう言った。
「どっ・・・・・・奴隷に・・・・・・」
「そうだ。人間の権利を放棄して、我々の飼い犬になるのだ」
室田が念を押すように言うと、私は、室田から視線をそらした。
「どうした。不服があるのか」
奴隷という、言葉に怯える私に考える暇を与えないように、室田は鋭い目で私を追い詰める。私はしばらくの間、悲しげに、その布の少ないタンクトップに、股下のないミニスカートという半裸の、身体を震わせていたが、やがてゆっくりと顔を上げ、
「わかりました・・・・・・それで結構です」
と返事を返した。
- [8] ベンジー
- 室田の待つ部屋に。恥ずかしい恰好で行ってしまったのだね。
電車に乗っていったのは、そういう理由があったわけだ。
自分が露出狂ではないことを証明したかったのだね。
でも、自分でも気づいていたのだろう。
本当に自分がどんなお女か。
それを室田に確かめて貰うのだね。
奴隷落ちの覚悟までして。
さて、結果はどうなるのかな。
- [9] 容子 証拠のビデオを撮られました
- 「よし、じゃあ、せっかくだから、証拠のビデオを撮ろう」
「ビデオ・・・・・・」
撮影されると聞いて、再び身を固くする私を尻目に、室田は、自分のカバンから私と鮫島達のプレイを、撮影するために用意していた、小型のビデオカメラと三脚を取り出し、慣れた手つきで三脚を組み立てていく。
「よし、これでいい」
三脚を組み立てた室田は、カメラモニターに私の全身が映っているのを、確認すると明るさなどの調整を合わせた。
「撮るのですか・・・・」
私は、セッティングを終えた、室田に不安げに尋ねる。
「ああ、証拠になるものを残した方が、お互いに後腐れがなくていいだろう?いやなのか」
覚悟してきたはずじゃないのかという室田の言葉に、私は顔を上げて室田を見た。
「わかりました。構いません」
「よし、じゃあ、まず、君はカメラに向かって、さっき私に言ったことを復唱してくれ、その後は私の質問に答えるだけでいい」
室田はそう言うと、自由回転式のモニターを私の方に向け、録画ボタンを押し自分も私の横に立つ。
「では、始めてもいいですか」
私はそう言って、隣に立つ室田を見上げる。
カメラが回り始めたことで、自身の決意はさらに揺るぎないものになったのか、モニターにはしっかりとカメラを、見つめる私の顔が映し出されていた。
「ああ、始めてくれ」
室田が、少し興奮気味にそう言うと、私はゆっくりと肯き、口を開いていく。
「私、曽賀容子は、本日、真実を追求し、社会悪と戦ってきた自分と、人前で恥ずかしい行為を繰り返されて感じてしまう自分と、どちらが本当の私なのかを確かめるべく、この恥ずかしい格好で、街を歩き、電車に乗って人前に、この自分の身体を晒してきました」
カメラに向かって、滑舌のよい声で語りかける私の姿は、凛としたものだった。
「そして、ただいまより、私が人前で恥を晒して、股間を濡らしていたのかどうかを確認するため、私が今、穿いているパンティーを、室田さんにチェックしていただきます」
しっかりした口調で、モニターにタンクトップにミニスカ姿の自分と、室田を映し出している、カメラに向かって言葉を続ける。
「もし、私のパンティーが濡れていなかった時は、必ず、私を報道の現場に戻していただけますね、室田さん」
そう言って私は、隣りにいる室田を見た。
「ああ、約束しよう、だが濡れていた時はわかっているね。君はここで絶対の服従を誓って、牝奴隷になるのだ」
私の、強い口調に負けないように、室田も大声でそう言った。
「わかりました。お約束いたします」
私もカメラの方を向いて、はっきりそう言った。
- [10] ベンジー
- 証拠のビデオまで撮ることになってしまったのだね。
カメラの前で、改めて宣言か。
恥ずかしい恰好で街に出て、電車に乗って来たことも、キャスターである自分と
恥ずかしい行為に感じてしまう自分のどちらが本当の自分か確かめたいなんて、
それだけで充分、自分は変態だと言っているようなものだと思うが。
その上でパンティーが濡れているかどうか、室田に確認して貰うことまで告げてしまったのだね。
心の内には、もう牝奴隷になった自分がいたのではないかな。
- [11] 容子 愛液検査
- 「では、確認を始めよう。そのタンクトップとスカートを脱いで、両手を頭の後ろで組んでくれ」
室田の言葉にゆっくり頷くと、タンクトップを頭から抜き取り、床に投げ捨てた。
次に、スカートのホックを外し、足元から抜き取る。
「よし、脚は少し開き気味でいいぞ」
私は、室田の言葉通り、両手を頭の後ろで組み、両脚を肩幅ほどに開いた。
ほとんど裸とはいえ、堂々とポーズをとった身体は、周りの注目を集めた。
「では、パンティーはハサミで切らせてもらうぞ」
室田の言葉に小さく、頷くと、何もかも覚悟を決めたかのように、そっと目を閉じた。
自分の股間の前に、しゃがみ込んだ室田の吐息を肌に感じながら、私の脳裏にキャスターとして、現場を駆け回っていた頃の記憶が蘇ってくる。
パンティーが濡れていなければ、自分はあの充実した現場に戻れるのだ、そう思うと私の心は期待に高ぶってくる。
だが、もしパンティーが愛液に濡れていたら、その時は全ての自由を奪われて、彼らの奴隷となり、彼らの変態的な行為の全てを、受け入れなければならない。
そのことを思うと、身体は恐怖に震え、両膝がガクガクと揺れ始める。
その一方で、乳房の揺れる胸の奥が妙に熱くなってくるのだ。
(ああ、私の身体はどうなっているのだろう)
そう思うと、哀しみに泣きたい気持ちになる。
だが、それを確かめるためにあんな恥ずかしい、ことまでしたのではないか、そう思って自分を奮い立たせ、覚悟を決めて天を仰いだ。
「よし切るぞ」
室田の声が響くのと同時に、パンティーの腰の部分が引っ張り上げられ、鉄のハサミが布を断ち切る音が二度部屋に響いた。
股間に冷たい空気が当たるのを感じた。
身体からパンティーが離れた後も、私は両腕を頭の後ろで組んだまま、じっと目を閉じて身動き一つしなかった。
「容子君。結果が出たよ。目を開けたまえ」
室田は、私の身体から剥がしたパンティーを眺めていたのか、しばらく時間を置いてから立ち上がると、優しい口調でそう言った。
私は室田の言葉に、ゆっくりと固く閉じていた目を開けた。
「あ、ああ・・・・・・」
目を開けた私は、室田の手で大きく広げられたパンティーの股間部分を見て、絶望したように嗚咽を漏らした。
大きく引っ張られた、幅十数センチの綿の布地には、その全てを覆い尽すように薄黄色の染みが広がり、さらに二重の布地でも吸収しきれなかったのだろう、その表面は粘着質の液体が埋め尽くし、それに部屋の明かりが反射して、キラキラと輝いていた。
「結果は出たな」
「ああ・・・・・・」
室田に追い打ちをかけられ、私は、後ろで腕を組むポーズをとったまま、恥ずかしげに身体を横に捻った。
「これはなんだ」
広げた股間部分を、私の眼前に突きつけ室田が言う。
「そ・・・・・・それは・・・愛液だと・・・・・・思います」
消え入りそうな声でやっと答えた。
「これは、どこから出てきたんだ」
「そ、それは・・・・・・」
室田の激しい追及に、私は全身を真っ赤に染めて室田から、視線を逸らした。
「こら、ちゃんと答えろ。約束だろう」
焦れた室田は、大声で嫌がる私を怒鳴りつけてくる。
「ああ・・・・・・」
小さなうめき声を上げながら、顔を上げると目を見開いて室田を見上げた。
「室田さん。お願いです。私に・・・・・・私に一分間だけ時間をください」
私の、まなざしのあまりの真剣さに室田は、「いいだろう」と言って頷いた。
「ありがとうございます」
- [12] ベンジー
- キャスターに戻れるか、奴隷になるかの掛かった確認作業だね。
結果はわかり切っているようなものだが、それでも容子は一縷の望みを繋いでいたということか。
室田の前でハダカになり、パンティーを切り取られる。
パンティーが濡れていないわけがない。
結果は見るまでもないってところかな。
さて、貰った1分を、容子は何に使うのかな。
- [13] 容子 牝奴隷宣言
- 私は、両腕を後ろで組んだ身体を起こして、再び大きく胸を張り、目を閉じた。
身体の動きの反動で乳房が揺れ、身体の一点に黒く生い茂る繊毛が眩しく光った。
(ああ、あんなに濡れてるなんて・・・・・・私、取り返しのつかないことをしてしまった)
目を閉じた私は、自分の愚かさを恨んだ。
だが、自分が自らの意志でこうしていることは、自分自身の言葉でビデオにしっかりと記録されている。
もう私は、室田達から逃げることは出来ない。
そう、彼らの行為を全て受け入れて、彼らの奴隷になるしかないのだ。
(どうしたの容子。貴女自身が選んだ道でしょ)
私の、心に自分の声が響く。
この言葉は、取材で深夜遅く帰宅し、一人暮らしの部屋で一人、泣き出しそうになる自分を、叱咤するために私が、いつも使っていた言葉だ。
そして、もしパンティーが濡れていたら、室田達の奴隷になる。
そう決めたのも私自身だ。
それは、淫らな自分と強気な自分、どちらが本当の自分か、頭でいくら考えても私が、その判断を自分自身の身体に聞くためにやったことだ。
(自分で決めたことだもの。結果が出た以上、それが本当の私なのよ)
私の身体が選んだ道は、キャスターとしての名誉や喝采を捨て、性の快楽だけを追い求めることなのだ。
私は、もう今までの全てを捨てる決心をし、ゆっくりと目を開いた。
「すみません。お待たせしました」
「決心はついたのか」
室田の言葉に大きく頷き。
「はい、室田さんが広げていらっしゃるパンティーについているのは、間違いなく、私の、厭らしいオマンコから出た愛液ですわ」
私は、ビデオカメラのマイクを意識し、かなりはっきりとした声でそう言うと、開き直ったように力強く胸を張った。
だが、その身体は屈辱に小刻みに震え、目から涙が流れた。
その反面、胸を張ると同時に、揺れた乳房の頂点にある小さな乳頭は、痛いほどに尖っていた。
この屈辱の中で、私の身体はマゾの性感に燃え上がっているのだ。
惨めな結果にも、精一杯強がる私の姿に、室田は同情するどころか、その嗜虐心をさらに燃え上がらせていた。
「このことは、何を証明しているんだ」
室田は、分かりきったことをもう一度聞く。
「ああ、それは・・・・・容子が厭らしい姿を見られて、感じていたことの証明ですわ」
私は、屈辱に胸を掻きむしられながらも、従順に室田の質問に答えていく。
「じゃあ、曽賀容子は露出狂のマゾヒストだと認めるんだな」
室田が楽しげに言うと、私は全裸で両腕を後ろで組んだままで、小さく頷いた。
「だめだ、ちゃんとカメラに向かって言うんだ」
「ああぁぁ・・・・・・」
あくまで私を追いつめる室田に、私は辛そうに天を仰いだが自分はもう迷わないと、決めたのではないかと自身に言い聞かす。
「室田さんのおっしゃる通り、容子は露出狂のマゾヒストです」
屈辱に震えながら、身体の芯がまた熱くなり始めた。
「よし、最後に俺の言うことを復唱するんだ」
室田は背後に回ると、耳元で囁き始めた。
「ああ、は、はい・・・・・・」
耳元で響く、隠語と猥語を混ぜ合わせたような、文章をとても聞いてられず、声を上げて首を振った。
しかし、被虐の性感に反応し始めた身体は、室田が命令する言葉が屈辱的であればあるほど、燃え上がっていくのだ。
「よし、言うんだ」
室田の口が耳元から離れると、私は、覚悟を決め、両脚を少し開いて、床を踏み締めるようにたち直す。そして、大きく胸を張り、視線をカメラのレンズに向けた。
「私、曽賀容子は、本日より皆様の牝奴隷となりました。私のFカップバストも、九十センチのヒップも、最近、敏感になったアヌスも、すぐに愛液を垂れ流す淫蕩なオマンコも、そして、陰毛の一本に至るまで、全てを皆様に捧げ、どんな厭らしいことや、恥ずかしいことでも、ご命令とあれば、喜んで実行する所存でございます。どうか皆様ご遠慮なく、このマゾヒストの容子に、厭らしいご命令をお与えください」
両腕を後ろで組み、ただでさえ、大きく前に突き出している、たわわな乳房を、さらに前へと突き出し、私はためらうことなく、一気に言い切った。
「ふふ、よし、もういいぞ」
室田は、満足げに微笑むと、ビデオカメラのスイッチを切った。
- [14] ベンジー
- とうとう認めてしまったね。
容子が露出狂のマゾヒストであることを。
取り返しがつかないことをしてしまったというわけだ。
室田とカメラの前で宣言してしまったのだね。
イジワルな室田は、さらに屈辱的な言葉を、容子の口で言わせたわけだ。
ここまで言ってしまった容子に、この先、どれだけ過酷な運命が待っているのだろうね。
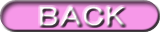 |